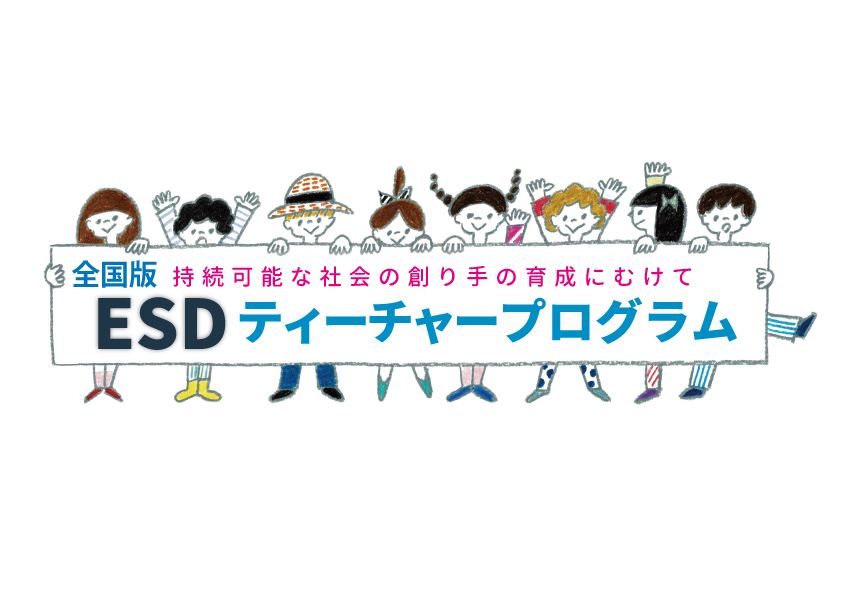ESDティーチャープログラム

2015年の国連サミットで採択されたSDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))においても持続可能な社会の実現に向けて、ESDが重要視されています。
また、2017年(平成29・30・31年)改訂学習指導要領には、持続可能な社会構築の観点が前文や各教科に盛り込まれ、ESDをどのように授業の中に取り入れていくかは、学校現場の課題となっています。
奈良教育大学では、ESDを体系的に学べる「ESDティーチャー認証プログラム」を展開しています(原則4月~翌3月の通年プログラム)。
本プログラム受講者は、学校や地域においてESDを適切に計画、実践できる「ESDティーチャー」として認証されます。
ESDと学校教育の関係
ESDとは、Education for Sustainable Developmentの略で、
持続可能な社会づくりの担い手を育むことを目的とした教育活動です。
日本では現行の学習指導要領の中に、ESDの考え方が組み込まれています。
また、日本には約1000校あるユネスコスクールが、ESDを推進していく拠点として位置付けられています。
ESDティーチャーとは
ESDティーチャーは、各学校でのESD推進を担う教員です。
教員としての基盤的な力量(学級経営、生徒指導、授業力、教科教育、子ども理解など)に加えて、豊かな教養(防災・減災教育、環境教育、世界遺産・文化遺産教育、国際理解教育、人権教育、福祉教育など)のもと、地域を教材化する視点を持ち、子どもの主体的な学びを引き出し、自らも持続可能な社会を担う一員として、ESDを実践していく力量を備えた教員を目指します。
《 ESDを指導できる教員に
求められる資質・能力 》
教師としての基盤的力量
+
豊かな教養や
持続可能な開発目標
(SDGs)への関心
+
地域で教材を発見し、教材開発を行い、
単元をデザインする力
認証プログラムについて
認証プログラムの内容は、対象によって2つに分かれています。
- 現職教員
- 奈良教育大学の在学生院生・教職大学院在籍者含む
プログラム概要
ESDティーチャー認証プログラムは、ESD連続セミナーを基盤としています。
このセミナーに一定回数参加の上、その他の要件を満たしていただくことで、「ESDティーチャー」として認証されます。認証は奈良教育大学が行います。
基本的な研修プログラムの内容
- SDGsと地球的諸課題
- ESDの学習理論
- 教材開発の方法
- ESD学習指導案の作成
- ESD学習指導案の検討
- 上記の内容をベースに全国各地の教育委員会等と連携した全国版ESDティーチャープログラムを実施しています。詳細は年度や開催場所等によって異なります。
- 過去の内容については、ESD連続セミナーのページをご覧ください。概要報告を掲載しています。
プログラムの種類と認証要件
ESDティーチャーコース
- ESD連続セミナーへの5回以上の出席とミニレポートの作成
- ESD学習指導案の作成
ESDマスターコース
- ESDティーチャーを取得していることが前提条件となります。
- ESD連続セミナーへの7回以上の出席とミニレポートの作成
- ESDティーチャー受講者の指導
- ESD授業実践と実践事例の報告
ESDスペシャリスト
- ESDマスターを取得していることが前提条件となります。
- ESD連続セミナーへの7回以上の出席とミニレポートの作成
- ESDティーチャー・マスター受講者の指導
- 研究会での授業実践の発表
プログラム概要
奈良教育大学の在学生(院生、教職大学院在籍者含む)が対象のプログラムです。
【2025年度の履修登録方法の説明会】については案内ページでご確認ください。
本プログラムは、下記の①~④で構成されています。
- 所定の科目の履修
- ESD実践への参加:学部生は1回以上、教職大学院生(現職教員以外)は2回以上
- ESD演習への参加:学部生は1回以上、教職大学院生(現職教員以外)は2回以上
- 学部生:ESD連続セミナー等への5回以上の参加とESD学習指導案の作成(3回生以上)
教職大学院生:ESD連続セミナー、授業づくりセミナーへの5回以上の参加と単元構想案及びESD学習指導案の発表
履修が必要な科目
必修科目
【学部生(下記より2科目以上)】
- ESD-SDGs基礎論
- ESD概論
- ESDと学校教育
- ESDと生活科・総合的な学習の時間
- 国連SDGs入門-「行動の10年」のためのサステナビリティの学び-
【教職大学院生(現職教員以外)】
- ESD-SDGsの理論と実践
選択必修
【学部生:環境教育、世界遺産・文化遺産に関わる科目(下記より1科目以上)】
- 山間地教育入門
- 持続発展教育と文化遺産
- 自然と地域の未来を探る
- フィールドワークで地域に学ぶ
- ESDと世界遺産
- ESDと気候変動
【学部生:ICT、防災教育に関わる科目(下記より1科目以上)】
- 情報社会と法・倫理
- 情報機器の操作
- 情報メディアの活用
- 教師のための情報モラル
- ESDと防災
- 地理学概論
【学部生:ユネスコスクール推奨科目(下記より2科目以上)】
- 人権と教育
- 生涯教育計画特講Ⅰ
- 文化遺産芸術学演習Ⅱ
- 日本国憲法
- 肢体不自由教育方法
- ユーラシア美術史
- キャリア形成と人権
- 知的障害教育方法
- アジアの中の日本美術史
- 教育人権アプローチ特講
- 生涯教育文化演習
- 地域文化論
- 教育人権アプローチ演習
- 校外学習指導特講
- 造形芸術学特講
- 文化遺産芸術学演習Ⅰ
- 大学での学び入門(文化遺産)
- 地理学野外実験
- 生涯教育文化特講
- 仮名書法論
- 仮名書道と実用書
- 国際理解地域研究
- 教育経営行政論
- 社会学
- 教育経営学特講
- ESD原論
- 教師のための多様性理解
- 教育経営学演習
- 水圏科学
- 生涯教育史特講
- 生涯教育政策特講
- 公衆衛生学
- 教育史特講
- 比較文化論
- 外国人児童生徒等のための日本語教育の基礎
- 特別支援教育原論
- 発達障害の心理学
- 知的障害の医学
- 肢体不自由の医学と心理
- 病弱児の医学と心理
- 病弱児教育方法
- 発達障害の理解と対応
【教職大学院生:専門科目(6科目)の中から3科目選択】
- ESDカリキュラムマネジメント
- ESDと総合的な学習の時間特講
- ESDと郷土教育・総合学習
- ESDと地域創生
- ESDとしての教科教育実践
- SDGsフィールドワーク
ESD実践
主に、学校現場におけるESD支援活動が“ESD実践”に当たります。
2025年度のESD実践の機会は、下記の通りです。
- ESD子ども広場
- ユネスコスクール野外活動等支援
- 東大寺寺子屋支援
- 被災地支援ボランティア
ESD演習
ESDに関するセミナーやレクチャー等が“ESD演習”に当たります。
修了の判定について
学部生の場合、プログラムは原則として3年をかけて履修を行います。
- 履修計画によっては短縮して履修をすることも可能です。この場合は、担当教員までご相談ください。
修了判定に必要なもの
- 必修・選択科目の履修を証明する書類(成績証明書)
- ESD実践、ESD演習で作成したポートフォリオ
- ESD学習指導案
提出〆切:各年度の1月末日
書類審査の上、年度末にESDティーチャー認定証を授与します。
履修モデル
本プログラムは、
- スタートアップ・プログラム
- プラクティス・プログラム
- グローバル・プログラム
の3つのステップにおいて、段階的な科目履修、ESD実践やESD演習への参加、ESDセミナーへの参加及びに指導案の作成を推奨しています。
① スタートアップ・プログラム
スタートアップ・プログラムでは、ESDプログラムにかかわる必修科目2科目とESD実践やESD演習への各1つ以上への参加を推奨しています。
- 必修科目については、上記「プログラムの概要」を参照してください。
- 以下は履修例です。
必修科目
- ESD-SDGs基礎論
- ESDと学校教育
② プラクティス・プログラム
プラクティス・プログラムでは、「ICT・防災教育に関わる科目」、「環境教育、世界遺産・文化遺産に関わる科目」より、各1科目以上の履修と、ESD実践やESD演習より各1つ以上に参加することを推奨しています。
- 選択必修科目については、上記「プログラムの概要」を参照してください。
③ グローバル・プログラム
グローバル・プログラムでは、「ユネスコスクール推奨科目」より2科目以上の履修と、ESD連続セミナーに5回以上参加し、ESD学習指導案を作成します。
ESD連続セミナーでは、現職教員、大学教員、学生が同じテーブルで、作成したESD指導案の検討を行います。
- 選択必修科目については、上記「プログラムの概要」を参照してください。